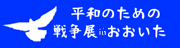Home > 核兵器・被爆・原発 > 被爆体験「言葉もなく」

被爆体験「言葉もなく」
杵築市 田中 美光 さん (大正15年生)
 昭和20年、18歳だった私は、現役兵として彗第8064部隊に入隊し、爆心地にほど近い長崎市の金比羅陣地に配属されていた。陣地には、7.5センチ高射砲6門が配備され、バラック兵舎も緊急事態に備えて砲則近くに建っていた。
昭和20年、18歳だった私は、現役兵として彗第8064部隊に入隊し、爆心地にほど近い長崎市の金比羅陣地に配属されていた。陣地には、7.5センチ高射砲6門が配備され、バラック兵舎も緊急事態に備えて砲則近くに建っていた。
8月9日午前11時、”戦闘配置”の命令を伝える鉄板を打つ音が激しく鳴り響き、私は兵舎から陣地へと全力で駆け上っていた。すでに、空を切り裂き落下してくる爆弾の「ゴー」という音が響いていた。走り出して間もなく、「至近距離だ。伏せろ!」と誰かが怒鳴る声に、私は咄嗟に地に伏せた。
人間というのは不思議なもので、危険を感じたとき、共に身を寄せ合おうとする群衆心理が働くようで、後に続く戦友たちが次々と私の上に覆いかぶさってきた。私が助かったのも、これが幸したのかもしれない。
次の瞬間、かたく閉じた瞼越しに、真っ黄色の光がはじけ、物凄い爆風が走り抜け、むせ返るような熱気を感じた。
気がつくと、私は近くの側溝に倒れていた。誰かが狂ったように「大丈夫か!大丈夫か!」と叫び続けている。私は、おそるおそる顔を上げ、あたりを見回し目を疑った。周囲の山の樹々は、すべて落葉し木肌は茶褐色に焼けていた。さつまいものイモヅルは黒く焼け焦げ、緑深く匂う風景は一瞬のうちに死の街に変わっていた。
被爆の実態について語ればきりがない。だが、原爆が投下され、悲惨な状況の中で、今でも忘れられない出来事がある。
被爆した兵士は倒れ、街は火の海と化している。動揺する私たちは、陣地に集められ、軍より2つの指示を受けた。
(1)壊滅した陣地の現況が漏れないよう、一般住民の陣地内立ち入りを禁止する。
(2)負傷者、特に火傷患者が水を要求しても安易に与えないこと。水を与えるとそのまま死亡することが多いので留意せよ。
やがて、私が倒壊した炊事舎の応急工事を命じられ復旧作業に従事していたとき、火傷や怪我を負った30名ほどの動員学徒が、足を引きずりながらやって来た。
「三菱兵器工場から、火の街を歩いてきた動員学徒です。水を飲ませてください。兵隊さん助けてください」
今にでも倒れそうな弱々しい声で水を求める学徒たちは、全身焼けただれ、顔の皮膚は落ち、髪の毛は焼け、男女の区別がつかなく、目ははれつぶれ、破れたシャツの背中は、ひどく出血していた。
哀願する弱々しい声に、私は被爆直後の指示事項を思い出していた。
「辛抱するんだ。今、水を飲んではいかん」
私の強い口調に学徒たちは落胆し、その場に座り込むものもいた。精根使い果たしたのだろう。だが、その中の1人が立ち上がった。花柄のカスリのモンペに白い開襟シャツ、焼け焦げて破れてはいたが、花柄の赤色が、私には印象的だった。引率の女教師らしい。
「火の中を潜り抜けてきた生徒たちです。水を飲ませて欲しいのですが・・・」
女教師はなおも水を求めた。
「火傷したものに水を飲ませると死を招くことがあるんですよ。生徒たちを死なせてはいけない!」
私は声を荒らげ、励ましながら言った。女教師は私の言葉をさえぎるように言った。
「生徒たちに水を飲ませて下さい。全責任は私が負いますから・・・」
私はその言葉に激怒し、激しい口調で問いただした。
「生徒が死ぬですよ!教師がその死にどのような責任を取ると言うんですか!」
女教師はうなだれ、そして今にも泣き出しそうにポツリとこう言った。
「ごらんの通り、みんな重傷者ばかりです。ここに来れば水がある。兵隊さんが守ってくれる。その一念で火に追われながら、お互い励まし合い、手を引き肩をかし、必死に歩いてきました。せめて一口、水を飲ませていただけませんか。水を飲んだら、これからみんなで天国に行きます。私が責任を持って天国に連れて行きますから・・・」
私はその言葉に愕然とし、心が激しく火照った。自分の死を覚悟してまで、教え子と一緒に旅立とうとしている教師の気持ちを察した時、誰が水を与えることを拒めましょうか。
「どうぞ、水をお飲みください。」
私は涙を堪えながらそう言って、学徒たちひとりひとりに水を配って行った。
人間の言葉の重たさと、いいようのない悲しみを知った日。昭和20年8月9日。この日を忘れることはない。
私は人間が好きだ。人間が好きになった原体験のひとつに、この女教師の姿がひそんでいる。語りつぎ、私は決して忘れない
*この文章は、大分県原爆被害者団体協議会が被爆50年(1995年)にあたり、体験を風化させないため、聞き書き出版した『いのちー21世紀への遺言』から、許可を得て転載しました。出版に当たり大分県生活協同組合連合会と大分県連合青年団が聞き書き調査に協力しています。