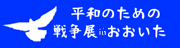Home > 核兵器・被爆・原発 > 被爆体験「今はただ、この平和がありがたい」

被爆体験「今はただ、この平和がありがたい」
津久見市 中岡 住男 さん (大正7年生)
私は7月26日ぐらいに召集で広島へ行った。白島の工兵連隊で、新しく召集された人たちだけで部隊が編成され、三佐田町の三佐田国民学校を宿舎にしていた。JR横川駅から歩いて10分、爆心地から2キロのところにあった
当日、所属部隊は九州かどこかに移動する予定であった。朝、移動物資を積みに広島駅へ向かうべく整列をしていた時に警戒警報が鳴った。当時広島には、一日に一機は偵察か何かに来ていたので、またいつものであろうと、校舎の二階に一時退避し、皆で雑談をしていた。
ピカーッと光って、そのあとドカーンとものすごい音がしたのは覚えている。しばらく意識を失っていたらしく、気がついてみると校舎はペシャンコになっていて、天井から落ちてきた大きな梁が体の上に乗っていた。幸いにも体の下の方に少し空間があり、動けないほどの怪我はしなかった。そこからやっと這い出して校庭に出たら誰もいなかった。
あたりの様子を見て、これは一体どういうことだろうかと思った。それまで長く東京におり、東京の空襲は始めから終いまで経験していたが、たった一発で校舎を押しつぶし、周囲の家々も、天守閣も何もかも、広島中を壊滅状態にするようなものは初めてであった。
ともかく自分一人であたりには誰も居ないので、どこかに行かねばならないかなと思い歩き始めたところ、後ろから「おーい、待ってくれー」と声がした。声をかけたのは尾道から召集された同じ部隊の人で重松さんという人だった。二人とも入隊したばかりで、道もよくわからないまま駅の近くまで出た。
ちょうど強制疎開で家が倒されたところに、広さは三畳ほど、深さ3メートル位の用水池があった。東京での空襲の経験から、これだけの水があれば火に巻かれても大丈夫だなと思ったのでここにおればいいと判断した。そのころには市内のあちこちから煙が立ち、消す者が誰もいないのでどんどん燃え出していた。
そのとき、「兵隊さん助けてちょうだい、兵隊さん助けてー」と女性とこどもだけが9人寄ってきたので、壕の中にみんなを入れて、重松さんが持っていた毛布を頭にかぶせて水をかけてやったりしていた。広島中の家がみんな焼けたのだから、それはものすごい熱風が吹いてきた。水をかけてもかけても、かけた先からカラカラに乾くので、しまいにはその用水池の中に入ってくみ出していた。
そうやって火と熱風とを相手に何時間戦ったかわからない。そのうちに燃えるものはみんな燃え尽きてしまい、熱風も収まったので駅の方に歩いていったところを、「おい、そこの兵隊。ちょっと来い」と憲兵から呼ばれ、連れて行かれそうになった。「ちょっと待って下さい。私たちのところにも怪我人が居るんです」と伝え、壕に戻り9人を一緒に連れていった。
その9人は、小学校五年生位の子どもからおばあさんまで女の人ばかりだったが、誰も真っ黒で、髪は焦げ、皮膚はただれてズルズルになってぶら下がり、中の肉が見えていた人もあった。言いようもない、見るに耐えないほど悲惨な様子をしていた。
憲兵から、信用組合をけが人の収容所にするから中を片づけるよう命ぜられ、建物の中に入るとガラスの破片や何やでいっぱいだった。どうにか片づけると、次はベッドの代わりにするために机を運び込め、けが人を机に寝かせろ、ほら次が来た、とてんてこまいだった。けが人はあちらこちらから、どんどん運び込まれてきた。
そうこうするあいだに、何時頃だったか夕立みたいなすごい雨が降り出し、そのひどい雨の中を走り回って、次々と運ばれてくる見るも哀れな人たちをどんどん運びいれた。あれがいわゆる「黒い雨」だったのだろう。
夕方になり、体はくたくたで腹も減り、どこかで休憩できないかと重松さんと二人で地下室に行って休んだ。夜になり一段落したので、本隊に戻るために、そこで救助活動をしていたという証明書のようなものを書いてもらい、その場を離れた。宿舎の国民学校の前まで帰ってみると、連絡員が来ており、その人に連隊の避難場所まで連れていってもらった。
そのときまで気がつかなかったのだが、「おまえ、火傷しとるじゃないか」と言われ、見ると首から上の右半分にひどい火傷をしていた。火傷には油がいいぞと誰かが言い、靴に塗る保革油をべったり塗られた。それが悪かったのか、けが人とそうでないものとに分けたときに、けが人の方に入れられた。その日はそのまま山の中で野宿をした。
あくる日、重い荷物を背負って暑い中を歩き回らされ、火傷のせいか熱は出るし、くたくたに疲れきってしまった。その夜はどこかの寺に泊まった。熱が出たと同時に下痢にも見舞われ、ひどい目にあった。
次の日、電車で可部というところに行き、亀山村の第一陸軍病院可部分院に収容された。そこで顔に塗っていた油をとってもらったが、薬がなかったので、しばらくは膿がでてウジがわくのではないかと思うほど腐っていた。やがてどこからか軟膏が手に入りそれでやっと治っていった。
そのうち終戦になり、まだ治りきらないまま八月の末ごろ津久見へ帰ってきた。何日かの休暇の後、退職金として百円ほどもらってそれで終わりだった。
火傷と体の疲れがひどくて少し目眩がするようなこともあり、帰って半年くらいはずっと休んでいた。地元の医者に診てもらおうとしたところ「そりゃあ新型爆弾のことは、わしにはわからん」といわれ、診察もせずに帰っていった。検査の結果白血球の数が異常に増えていると言われたことがあるが、火傷以外の自覚症状はなかった。
被爆の後遺症は、強いて言えば血圧が低いことだろうか。これといって具合の悪くなることもなく就職もし、結婚もした。被爆したことで差別されるようなこともなかった。
東京大空襲での経験がずいぶん役に立ったし、自分たちは運も良かったんだろう。「兵隊さん、助けて」と言ってきた人たちは、おそらくあの後何日も生きていられなかっただろう。今はただこの平和が有り難いだけである。
*この文章は、大分県原爆被害者団体協議会が被爆50年(1995年)にあたり、体験を風化させないため、聞き書き出版した『いのちー21世紀への遺言』から、許可を得て転載しました。出版に当たり大分県生活協同組合連合会と大分県連合青年団が聞き書き調査に協力しています。