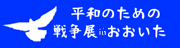Home > 核兵器・被爆・原発 > 被爆体験「愛し子偲びて五十年」

被爆体験「愛し子偲びて五十年」
大分市 安東 二三子 さん (明治38年生)
いとしい子よわが名を呼びて助けをば求めつかれて命絶えたるや
忘れもしないあの日の早朝、警戒警報が出たので防空壕へ入りました。まもなく解除となり、朝食をとり主人は役所へ、子ども(小四)は学校へ。疎開で長い休みになっていたのがその日から始まり、元気に出掛けたのでした。
二人を送り出し炊事場で片付けをしていると、突然異様な閃光がひらめいたので『あら何かしらん』と思った瞬間、ガラスは割れ瓦は飛び散り、急いで家を飛び出しました。何が何やら分からぬまま防空壕へ入りましたが、外は静かで何ごともないちょうなので、一安心して外へ出ました。
そこへ主人が帰って来て「英雄は帰ったか」と申しますので「まだですが」と言いましたら「それは大変だ、外は大火事になっている」との言葉に、この時ほど驚いたことはありません。
夢中で官舎門へ駆けつけて見たら、外は火の海。(官舎は高塀で囲まれ類焼を免れた)前の住吉川に無数の人たちが浮きつ沈みつ流れて行きます。路上には裸の人たちが仰向けに転がっていますが、少しも怖くないのが不思議です。あの夏は暑い日が続いていたのですが、暑さも感じないほど緊迫した状況でした。
英雄の学校は、廃業した銭湯を利用した代用校舎で、私は一度も行ったことがありませんでした。見当をつけて駆けて行きましたが、とても寄り付けなく、子どももそれきり帰って来ませんでした。
翌日役所の方々にお願いして現場に行って見ましたが、熱くてまだ手が付けられず、二、三日してようやく風呂場の焼け跡をフルイにかけたところ、四人分のお骨が出ました。「お心当たりの方はお預かりしてありますから」の立札も無駄になって、一人も来なかったのをみますと、御家族の方々も被災して亡くなられたのだと思います。それで学友四人の遺骨は、私の郷里の累代墓に懇ろに葬ったわけです。
その後、助かった子どもたちから、英雄の「カアチャン、助けて」と叫んだ声を聞いたとの話を聞きました。両親がありながら救出が間に合わなかった無念、親の思いをお察し下さい。
しかしながら実際に子どもの遺骸を見ていないのでどうしても信じることができず、あらゆる収容所を何日も捜して回りました。何処の収容所も担架で担ぎ込まれる人、死んで運び出される人等で混雑を極めておりました。収容者は人相も分からぬように焼けただれ無意識にうわごとを言ったりうめいたりで、この惨状を見ては却って即死した方が良かったのではないかと思いました。
それから久しく、ラジオの尋ね人の時間にも、もしやと気をつけていましたが、五十年過ぎた今日まで、とうとう帰ってきません。あれほど郷里に疎開したがったのに、「死なばもろとも」の浅はかの考えから、あたら幼い命を戦争の犠牲にしたことは、何としても愛し子に申し訳ない次第で、今だ亡き子の歳を数えて暮らしております。
昭和二十年に入って本土空襲も激しくなり敗戦の気配も感じられるようになっていましたが、来る敵機は皆広島の上空をかすめて、中国や関西方面を爆撃するので、少し横着になっていた矢先のことでした、
こんなかたちで戦争が終結するなど思いもよらなかったです。二十年八月六日、あの惨事は終生忘れることが出来ません。
みんな、叫ぶことばは一緒です。「戦争は二度と起こさない」。来る九十歳。世界平和を心から願うものでございます。合掌。
*この文章は、大分県原爆被害者団体協議会が被爆50年(1995年)にあたり、体験を風化させないため、聞き書き出版した『いのちー21世紀への遺言』から、許可を得て転載しました。出版に当たり大分県生活協同組合連合会と大分県連合青年団が聞き書き調査に協力しています。