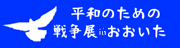Home > 核兵器・被爆・原発 > 被爆体験「「絶対、広島の話はせんぞ」と思った私が、今語るのは・・・」

被爆体験「「絶対、広島の話はせんぞ」と思った私が、今語るのは・・・」
別府市 小島 正司 さん (大正11年生)
昭和二十年四月、船舶砲兵だった二十三歳の私は、山口県の本隊から下士官養成教育のために、広島市比治山付近の皆実町にある船舶通信連隊に転属しました。
それから五ヶ月目の八月六日朝、教育隊の上等兵以下四十数人が、司令官による最後の検閲を受けるため、営庭に二列縦隊に並んでいた時のことです。警報のサイレンが鳴らぬのに、飛行機が上空に見え、霧みたいなものがパッと拡がりました。顔をなでて手をおろすと同時に、ピカッと光って、伏せたのか吹き倒されたのか今だに判断がつかないのですが、倒れて気を失い、目が覚めたら、あたりは真っ暗でした。
まず一番に、逃げねばならぬと思い、水の中に入れば火が来てもなんとかなると、営庭の真ん中にあった防火用水の方向に走りました。前がよく見えないので、目をやられたんだなあと思いながら、一生懸命目をこすっていました。
それから十四、五分後、空を見上げたら、ポッポッと光が見え始め、だんだん明るくなってきて、埃や煙が上がっていくのが見えました。防火用水の左の方にあった本部兵舎が無いのに気付き、おかしいなあと、すっかり明るくなってよく見たら、押しつぶされたような形で一階くらいの高さになっていたのです。爆弾にしては壊れてないし、吹っ飛んでもいなかったので、きっとものすごい圧力がかかったのでしょう。瓦も飛んでないで、ずり落ちたようになっていました。
一時間ほど後、司令官が負傷したとの連絡があったので、検閲は取り止めになりました。自分の持ち物を取りに行ったのですが、兵舎は押しつぶされていて、中には入れませんでした。それで、そのまま非難しようと、比治山の壕へ向かいました。途中、市民に会いましたが、夏の薄着のため、火傷をしたところの皮がはげて白くなっているのが見えました。「兵隊さん、助けてー、助けてー」とそれはあわれなものでした。それぞれ光を受けた側が焼かれているのです。真正面に光を受けた人は目が開かないし、口を開けていた人は内側まで火傷していました。私は顔の左半分と左手を火傷しました。
前の晩の呉への激しい空襲のため、就寝時間は翌朝の八時まででした。兵舎の中にいた兵や、家の中にいた市民には怪我人が多く、頭、耳、手足などをやられ、それはひどい有様でした。柱の間に挟まれて、出るに出られず焼け死んだ人もかなりいたと思います。立っていられなくて砂や土の上に寝転がる人もいました。日陰に行くだけの気力もない人が沢山いました。
私も他人を救護できる状態ではありませんでした。火傷には油がよいということで、スピンドル(鉄砲の油)をつけろと教官に言われ、三角布に油をつけて顔や手を包みました。痛みがひどく、顔の左側がヒリヒリしましたし、左の耳がペタッとくっついている状態でした。その晩は痛くて眠れませんでしたが、油を付け替えるとちょっと痛みがやわらぎ、一日の疲れもあって、そのまま眠ったようです。
翌朝、起床してみると比治山に登って来ていた黒山のような市民の半数以上が死んでいました。あたりは足の踏み場も無いほどでした。朝食の時、あれは新型爆弾だったと聞きました。九時頃トラックが来たので、四十数名で己斐という町の小学校へ行くと、そこは野戦病院のようになっていました。
二日ぐらい経つと顔の火傷の内側がムジムジと痛痒いのです。兵隊同士で顔のカサカサをはいでみたら、蛆がわいていました。衛生兵に「薬をくれ」と言ったら、「なぜ蛆を追わんか」と逆におこられました。乾いてきたカサが顔の形どおりにはがれるのです。私は二回くらい取りました。
その野戦病院には市民も多勢いて、昨日は何人亡くなった、今日は何人死んだという状況で、次から次へと火葬にされていました。
二十一日頃、連隊復帰の命令を受け、二十四日に広島を出て山口の本隊へ戻りました。九月六日でした。それまでは、ただ帰りたい気持ちでいっぱいでした。九月九日には今の新別府病院(元陸軍病院)に入院できました。病院はいっぱいでしたが、新型爆弾研究のためか、優先して入れてくれたようです。
それから約半年。三月二日頃に退院したと思います。早く就職しないと、というあせりもあり、包帯を巻いたまま中山香の農会(今の農協)に勤めました。包帯が取れるまでの一年、完全に治るまでには約五年位かかりました。包帯がとれるようになっても、その後二、三年は包帯をして顔を隠していました。まだ嫁をもらう前でもあり、被爆者と思われたくなかったからです。
本当は、原爆の話はしたくありません。被爆を体験し、広島の惨状を見たとき、もう絶対、広島の話はせんぞ、と思いました。それはむごいものでした。それに私には、被爆者を救助できなかった心の痛みもあるのです。あの当時の被爆者達の顔が浮かんできて、今でも震えがきます。被爆した人たちは、みんな同じだと思います。年二回の健康診断で会っても、どこで被爆したかは話しますが、その時どうであったかは、全く話しません。思い出したくないからです。時が経つほど、その気持ちは強くなるばかりです。
*この文章は、大分県原爆被害者団体協議会が被爆50年(1995年)にあたり、体験を風化させないため、聞き書き出版した『いのちー21世紀への遺言』から、許可を得て転載しました。出版に当たり大分県生活協同組合連合会と大分県連合青年団が聞き書き調査に協力しています。