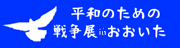被爆体験「悪夢」
大分市 藤田 久子 さん (昭和2年生)
昭和二十年八月六日、私は当時十七歳。女学校を卒業してすぐのことでした。
被爆から五十年。遠い記憶になりましたが、爆心地から一・五キロの地で体験した悪夢のようなその日のことは、忘れることができません。
 「ピカーッ」と、ものすごい光と音に、私は何がおきたのか解らず、しばらくボーッとしていたと思います。
「ピカーッ」と、ものすごい光と音に、私は何がおきたのか解らず、しばらくボーッとしていたと思います。
気が付くと辺りはまっ暗。二階に寝ていたはずなのに、家はつぶれて下に落ちていました。
着ていた夏ぶとんが手にふれたので、それを掴んで跣で外に飛び出しました。もう、前の家は燃えていて、自分の家を振り返る気にもならず、ただ歩きました。
一瞬のうちに焼けてしまったのでしょう。“いなばの白うさぎ”を思い起こすような、体は焼けただれ皮膚が垂れ下がった人たちが歩いていました。
私も爆風のため裸になっていましたが、髪の毛もなくなっているような気がして、怖さで夜まで頭に手をやることができませんでした。
周りは火の海。黒い雨が降ってきて、上空では飛行機がグルグル旋回しており、みんな自然に川へ向かって逃げました。
土手にはたくさんの人が重なり合って倒れていました。まさに生き地獄の様でした。 三日位広島にいたでしょうか。羅災証明が発行されてからすぐに郷里の佐伯に向かいました。
三日位広島にいたでしょうか。罹災証明が発行されてからすぐに郷里の佐伯に向かいました。『早く親の元へ帰りたい』、思いはそれだけでした。
しかし、楽な旅ではありませんでした。岩国あたりで汽車がトンネルの中でとまってしまいました。上空で空中戦が始まっていたのです。そんな状況下、とにかく『同じ死ぬなら少しでも佐伯の近くで』と、汽車を乗り継ぎました。
佐伯ではすでに、広島にはこの先草も生えない特殊な爆弾が落とされたと風評が立っており、「よく生きて帰って来た」と喜ばれました。
戦後は、体も弱く不安は常にありましたが、特別な病気もなく、子どもにも恵まれ幸せな日々を過ごしています。
今思うと、被爆時、家の中にいたことや、夏ぶとんをかぶり黒い雨を防げたこと、早く広島の地を去ったことなどが幸いしたのかもしれません。
しかし、心の傷は深く、当時のことは、めったに話すこともありませんでした。
キノコ雲もみました。丸裸で真赤に焼けただれて歩いている人もたくさん見ました。途中まで一緒に歩いていた二人の方は、ご無事だったんだろうか。「お姉ちゃん、お姉ちゃん」とまつわりついて来た子どもたちは、どうしただろう。赤ちゃんを抱いたお母さんの「助けて」という声が今も耳に残り忘れることが出来ません。それらを振り切って逃げた自分を悔いたこともありました。本当に悪夢でした。戦争はいけません。平和が一番です。絶対戦争をしてはいけません。
*この文章は、大分県原爆被害者団体協議会が被爆50年(1995年)にあたり、体験を風化させないため、聞き書き出版した『いのちー21世紀への遺言』から、許可を得て転載しました。出版に当たり大分県生活協同組合連合会と大分県連合青年団が聞き書き調査に協力しています。