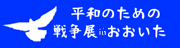Home > 核兵器・被爆・原発 > 被爆体験「残された者の使命」

被爆体験「残された者の使命」
日出町 木付 薫 さん (大正4年生)
私は、昭和20年8月6日広島に落とされた原子爆弾により被爆し、家族4人を亡くしました。
私が被爆したのは、爆心地より1.2キロメートル、家族はわずか700メートルの位置でありました。当時31歳であった私は唯一1人生き残り、毎年8月が近づくと今も当時の記憶が蘇ってきます。
昭和20年8月6日部隊(暁6180部隊)へ出勤する準備をしていた時警戒警報のサイレンが鳴った。7時30分頃だったと思う。空を見ると飛行機が2機飛んでいたが、空襲警報には至らず、数分後に解除され、ホッとした気持ちで一息つき、再び出勤の準備にとりかかった。
 大手町市役所前から部隊のある比治山まで3キロメートル程の道程であり、私が宇品経由の電車で勤務先の部隊へ赴いてる時であった。勤務先の電停付近まで来たとき、一瞬青い閃光が走った。瞬間、私は電車の変電気がスパークしたのかなと思ったが、電車のガラスはすべて飛散しており、運転席を見ると、もうそこに運転手の姿はなかった。電車は今来た鉄路ゆっくりと逆に動き出した。ただごとでないことが、乗客たちの悲鳴から感じとれた。
大手町市役所前から部隊のある比治山まで3キロメートル程の道程であり、私が宇品経由の電車で勤務先の部隊へ赴いてる時であった。勤務先の電停付近まで来たとき、一瞬青い閃光が走った。瞬間、私は電車の変電気がスパークしたのかなと思ったが、電車のガラスはすべて飛散しており、運転席を見ると、もうそこに運転手の姿はなかった。電車は今来た鉄路ゆっくりと逆に動き出した。ただごとでないことが、乗客たちの悲鳴から感じとれた。
我先にと電車から外に出ようとするが、出入り口は狭く、思うように出ることもできず、降りたというよりせりおとされたので怪我人も多く、年寄り子供らは人の下敷きになり、苦しみながら助けを求めていたが、皆が割れたガラスで怪我をしており人助けどころではなかった。私の怪我は軽い方であったが、それでも目の上にガラスの破片が刺さり、顔は鮮血で赤くなっていた。
全員が車外に出れたが、外は白煙と砂塵で数メートル先も見えない有様で何が起きたのか判らず、互いに顔を見合わせるものの、ただ呆然としてるだけだった。あの恐るべき原子爆弾が落とされたことなどこのときは知る由も無かった。街全体から白煙と砂塵が立ち上り、倒れた家々からは火が燃え上がっていた。見上げた太陽は、まるでおぼろ月のように見えた。
この中を右往左往する被災者は、何が何だか判らないまま、我先に安全な場所を求めて山手の方や川へと無言で走っていく。倒れた家の下敷きにでもなっているのか、助けを求める声も聞かれた。電車の軌道沿いに立っていた電柱は、折れたり横倒しになったりで、何一つまともな物はなかった。
私はタオルを取り出し、マスクの代わりにして部隊へ急いだ。何度か通ったことのある近道を通り、松林の中に入ると松の大木は爆風でなぎ倒されていた。先に逃げた人が倒れた松を手摺り代わりにして避難したのか、手の触れる所がないほど鮮血にまみれ、まだポツリポツリと流れ落ちているところもあった。私は無我夢中で松林を抜け部隊へたどり着いた。バラック建の兵舎は吹き飛び、裏側の杉の木にひっかかっており、爆風の強烈さを感じた。部隊では無事であったもの同士「良かった。良かった」と手を握りしめ、肩を叩きあって喜び励ましあった。
その後東京の司令部より「特殊爆弾ではないか」という知らせがあり、私が遭遇したのが原子爆弾であったことが分かったのは次の日のことであったが、市民は全く知る由もなかった。市民はピカッと光ってドンと爆発したので、いつのまにか「ピカドン」と呼んでいた。
私たちはさっそく被災者の救援活動に移った。
上空には6、7千メートルの所で「きのこ雲」が内から外へとむくむく盛り上がり、その雲の至る所に七色の虹が見え、異様な美しさを醸し出していた。
私たちの所で黒い雨が降ってきた。後で聞いたところによると、広島市内より数十キロ離れた所では黒い大雨が降ったそうだ。この「きのこ雲」は1万メートルくらい上昇し、そのまま遠ざかって行った。市内では、この異変に関係ないように8月の太陽が再び顔出し、炎熱は容赦なく私たちの上から照り続けた。
広島市のはずれ、比治山公園の道路の両側に、県庁が使用するために掘った防空壕が何十ヶ所とあり、それを目当てに負傷者が我も我もと駆けて来た。暑い季節で薄着だったし、爆風や熱風(約3千度くらいあったと聞いている)でその衣服はほとんど剥がされ、甚だしい者は一糸まとわない姿の者も数多くいたが、恥ずかしいなどと考える余裕もなく、ただひたすら生死の境を走り続けているように見えた。
私たちの姿を見てホッとするのか、「兵隊さん」と叫びながら倒れ込んでくる。その一人一人がまともな人間像をした者はなく、余りにも変わり果てた姿を見て、この爆弾の威力を見せつけられた思いがした。
負傷者の中には男女の別さえ判らない程全身流血で、赤い水玉模様や、真っ赤な着物でも着ているように見える人もいた。火傷で腕の皮膚が指先6、7センチ程垂れ下がり、それをブラブラ振りながら気力一本で走ってくる姿は、まさに生き地獄であった。
「子どもを助けてください」と走り込んできた母親がいたが、すでに子どもは死んでいた。しかし、子どもは爆弾によるものではなく、母親がしっかり抱き締めていたため、愛情により絞め殺された状況であった。また逆に、死んだ母親の乳房にすがりつく乳幼児の姿も見られた。
水を求めてうめく者、大声で肉親の名前を呼びながら苦痛を訴える者、顔が変形してしまい、名前を言わなければ肉親でも見分けのつかない程の人々で、それは悲惨なものだった。
こんな状況の中、私たちは休む暇もなく救援活動を続けた。負傷の程度により軽傷者をA、重症者をB、生命の保証ができない者Cと区分して、治療が始まった。火傷をした患者は、水を人一倍求めたが、A、Bクラスの患者には辛抱してもらい、Cクラスの患者のみ水を飲ませた。水を与えた者のほとんどが3分以内に息を引きとった。その数は計り知れなかった。
A、Bクラスの者を防空壕に運び込んだが瞬く間に壕はいっぱいになった。収容された患者は痛さに我慢できず、「ウッ、ウッ」とうなる声が段々に大きくなっていく。やがて壕の中は異臭が漂い始め、うなり声は叫び声にも似た騒音と化していった。まるで、地獄の底から、この苦しみが地上の人間の頭の奥深くに響けと、死に者狂いで訴えているかのようであった。その姿は看護するものの胸をも強く打った。手当するにも薬や包帯は殆ど無く、赤チンを塗るぐらいであった。
この状態がしばらく続き、ようやく新しい患者の数も少なくなり、肉親との再会に抱き合って涙ながらに語り合う光景も、いたる所で見られる様になった。
いくらか落ち着くにつれ、緊張が緩むと今度は家に残した家族の安否が気遣われてきた。「無事でいてくれ」と、私ははやる気持ちで帰途に着いた。すっかり焼野ヶ原となった市内には、もはや昔の面影はどこにもなかった。途中の道路には死体は勿論のこと自転車、三輪車、荷車、リヤカー等全部横倒しになり、足の踏み場もない様に思われた。
丸焼けになった電車の中には、出遅れたのか、窓に両手をかけたまま白骨化した者や多分熱線に当たったのであろう、半身真っ赤になり焼け死んだ者もあった。
一瞬の内に灼熱地獄と化し、苦痛と余りの暑さに水を求め、市内を流れる川までやっとたどり着き、そこで力果てた人々の死体は計り知れない。川は、水面が見えないほどの死者の数であった。
川岸では水を求めにやってきた人々の死体が折り重なっていた。そのほとんどは素足のままだった。中には、そのすぐ目の前の水たまりの水を飲もうと一寸ずりで這い進んでも届かず、恨めしそうに見つめて死んでいる者もいた。
やっとの思いでたどり着いた大手町市役所前の我が家付近は人影もなく、我が家も火災で丸焼けとなっており、見るも無残な跡になっていた。焼け跡にたたずみ家族の姿を探したが、この様子では全員助からなかったことは十分察せられた。炊事場であった所を見つけ出し、少し探してみると日頃使っていたアルミの釜が出てきた。中には水や食器が入っていた。アルミのヤカンはローソクでも溶かしたかの様に変形していた。
近所では爆風で2階部分が吹き飛んだものの、1階にいたため助かった者もいた。
母は子どもを連れて外にいたことまでは判った。妻は、子どもは、母は、と懸命に探したが、見つけ出すことが出来なかった。
そのまま死体収容所に行ったが、その殆どが身に付けていた物でしか判断できない状況であった。妻、子ども2人、そして母を一瞬にして亡くしてしまい、立ち去りがたい思いを残し、死んでいった家族の冥福を祈りつつ、私は再び部隊へと向かった。後で聞いた話であるが、妻が他の場所へ移送され三日間ほど生きていたそうだ。
同年8月15日終戦を迎え、部隊での残務整理のため、私が郷里日出町藤原に帰ってきたのは、その年の12月でした。
郷里に帰り一番心配したことは、果たして再婚できるか否かでありました。原子爆弾による後遺症が懸念されたのです。再婚できたとしても、生まれてくる子どもに何らかの症状が出るのではないかと心配したのです。再婚後4人の子どもに恵まれました。心配された症状は誰にもなく、現在全員が元気に過ごしております。
しかし、私には被爆後3年目頃から後遺症に悩まされた日々がありました。突然ピンク色の汗をかきだしたのです。病院に行っても原因がつかめず、この症状は4ヶ月ほど続きました。その後、今度は悪寒に悩まされました。夏に綿入れを羽織っていないと過ごせない毎日で、食欲も平常の半分以下という症状が、これも3ヶ月程続きました。それから2年後、貧血症状が出て、怪我をすると血が止まらず、2時間くらい押さえておいてやっと止まる状態が40日ほど続きました。この間は怪我が恐く、何をやるにも引っ込み思案の毎日でした。その後は特に症状らしきものはなく、現在まで元気に過ごしております。
私たち原爆被爆者は、この体験を全世界に向かって語り続け、二度と戦争がこの地球上に起きない様、全国民と共に一致団結して、反核運動呼びかけています。それは広島や長崎で無残に散っていった沢山の尊い命の代弁者として、これからの世界を担う青少年に言い伝えていくことが、私たちの使命だと思っているからです。「戦争」の二文字を無くし、「平和」の二文字を永遠のものにできるように願っています。
*この文章は、大分県原爆被害者団体協議会が被爆50年(1995年)にあたり、体験を風化させないため、聞き書き出版した『いのちー21世紀への遺言』から、許可を得て転載しました。出版に当たり大分県生活協同組合連合会と大分県連合青年団が聞き書き調査に協力しています。